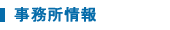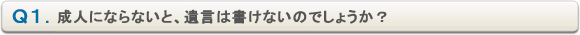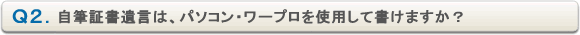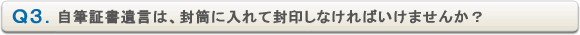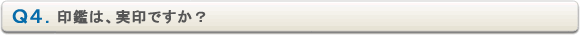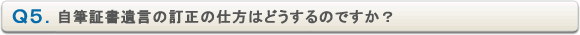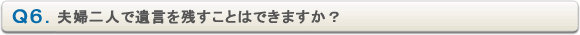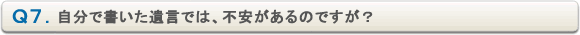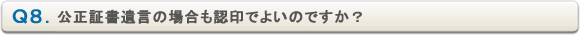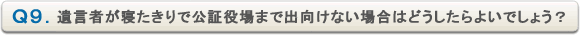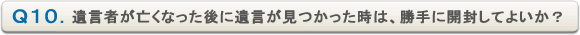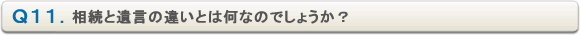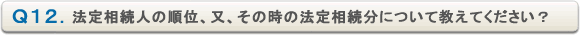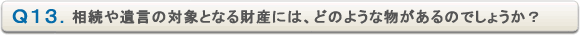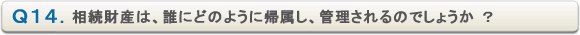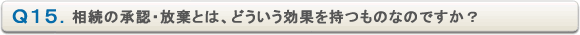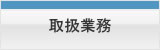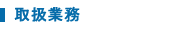谷町国際法務行政書士事務所
〒540-0012
大阪市中央区谷町2-3-7
クローバーハイツ大手前402
TEL:06-4790-8048
FAX:06-4790-8049

「遺言書」という言葉はよく聞きますし、知らない方はいらっしゃらないと思います。しかし、具体的な書き方となると、どうでしょう?
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。そして、それぞれに厳しい要件があり、要件が欠けると無効になったりします。
遺言書には、相続のときのトラブルを減らす効果がありますが、遺言書の要件が欠けると、せっかくトラブルをなくすために書いたのが、反対にトラブルの元になったりします。それでは書かなかったほうが良かった・・・なんてことにもなりかねませんね。
自筆証書遺言であれば、本を見ながらお一人で作成することも可能ではありますがせっかく作成するのなら、専門家にサポートしてもらったほうが安心確実です。また、公正証書遺言ともなると、なかなかお一人では心配です。専門家のアドバイスを得ながら作成することをお勧めします。
当事務所は、相続・遺言書作成を専門に行っている行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。
-
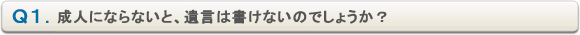
-
満15歳になれば、遺言をすることができます。
-
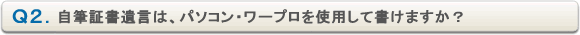
-
自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています。(民法第968条)パソコン等の使用は、後記記載の秘密証書遺言のときは可能です。
-
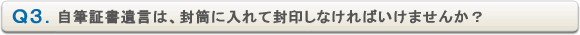
-
必ずしも封印する必要はありません。
但し、封印のある遺言書は、遺言者が亡くなった時、家庭裁判所に提出して相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。これを検認手続きといいます。
管轄裁判所は、遺言者の最後の住所地です。因みに、家庭裁判所外において開封した者は、過料に処せられます。(民法第1004及び1005条)
-
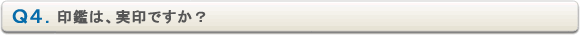
-
認印でかまいません。
-
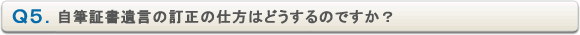
-
加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。(民法第968条2項)
-
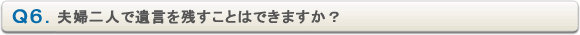
-
遺言は、あくまでも本人の意思による必要があるので、共同ではできません。
-
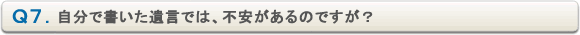
-
公正証書による遺言がよいでしょう。
-
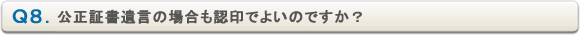
-
この場合は、遺言者は実印が必要です。2人の証人は、認印でかまいません。
-
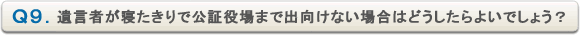
-
遺言者の依頼によって、入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。
-
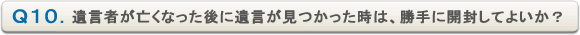
-
公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、亡くなった人が住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に、遺言書検認の請求をしなければなりません。
-
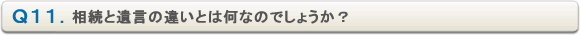
-
相続と遺言(死因贈与も含む、以下同じ)は、どちらも人の死後に残された財産を、誰がどのように承継するかを定めた民法上の規定です。
相続は、法律上当然に相続人に、財産が承継される規定であり、遺言は、故人の生前の意思表示に基づいて、財産が承継される規定です。
どちらも開始する原因は、人が死亡した時です(民法第882条・民法第985条)。
相続における対象者は、遺族であり、遺言の対象者は、特に特定されておりません。
具体的な相続の開始原因
- 自然死亡
- 認定死亡(戸籍法第89条)
- 失踪宣告(民法第30条・第31条)
- 同時死亡の推定(民法第32条の2)
同時死亡と推定される者の間では、相続関係は、生じません。
-
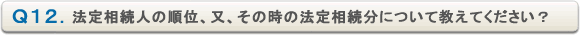
-
法定相続人の順位やその時の法定相続分は以下のようになっております。
1.法定相続人の順位
- 配偶者は、常に相続人となります(民法第890条)(内縁の妻は、対象となりません)
- 血族相続人
・第1順位 子
常に相続人となります(民法第887条1項)養子も相続人です。(養子は実親の相続をする権利も有します。)
子には、胎児を含みます。(民法第886条)但し、特別養子は除く。(民法第817条の9)
・第2順位 直系尊属
子供がいない場合に相続人となります。(被相続人に近い者が先)
・第3順位 兄弟姉妹
子供も直系尊属もいない場合にだけ相続人となります。
- 非嫡出子も相続人ですが、相続分は嫡出子の2分の1(民法第900条4号但し書)。相続人としての地位は、嫡出子と同じ。
- 代襲相続
相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡し、又は欠格・廃除により相続権を失った場合において、
その者の子が代わって相続人になる場合のこと(民法第887条2項・3項、889条2項)。
・相続人の直系卑属(子供)の場合は、どこまでも続きます。
(民法第887条3項、再代襲・再々代襲)
・兄弟姉妹の子も代襲相続出来るが、その子の子には、代襲相続権はありません。
(民法第889条2項)。
・代襲者の相続分は、被代襲者と同じ。被代襲者が、放棄した時は、代襲原因となりません。
・子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数に応じて均等分割が原則。
子の場合は、嫡出子と非嫡出子とで差が出ます。
・代襲相続においては、被代襲者の相続分を代襲相続人の人数に応じて均等分割。
2.法定相続分(昭和56年1月1日以降)
子及び配偶者が相続人であるときは、各二分の一
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者は三分の二 直系尊属は三分の一
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者は四分の三 兄弟姉妹は四分の一
(民法第900条)
-
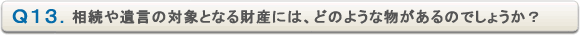
-
被相続人の財産に属した一切の権利義務(民法第896条)をいい、積極財産としてのプラス財産(現金や不動産など)と消極財産としてのマイナス財産つまり債務(借金など)があります。
厳密には権利義務とはいえないものであっても財産法上の法的地位といえるものならば相続の対象となります。(例:占有者の善意悪意、物上保証人としての責任、契約申込者の地位など。)
相続財産に含まれないもの
- 財産に関しない権利義務(民法第896条本文)
- 被相続人の財産に属さない権利義務(民法第896条本文)
まぎらわしいものとして 香典・生命保険金請求権・死亡退職金その他の遺族給付金
- 財産上の地位だが、本人の死亡により消滅することが決定しているもの(一身専属的な権利義務の法定例といえる)
- 一身専属的な権利義務(民法第896条但書)
- 祭祀財産(民法第897条)
ケースバイケースのため注意が必要なもの
- 借家権
- 社員たる地位(社員権)
- ゴルフクラブの会員たる地位 など
→ (1)の借家権について、内縁の夫や妻または同居の者の借家権の承継は、相続に基づくものではなく、同居者保護の観念から、法的構成がなされています。
-
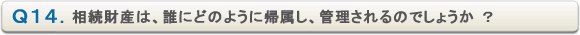
-
原則:当然承継
相続人は、相続開始の時から当然に相続財産を承継する(民法第896条本文)
- 共同相続財産の帰属
相続人が複数人いる時には、被相続人の相続財産(債権債務)は、個々の相続人への具体的な帰属が決まるまでは共同の管理のもとに置かれます。
- 共同相続財産の管理
複数の相続人がいる時には、被相続人の相続財産(債権債務)の管理については、管理行為として、保存行為・変更行為・その他の管理行為ができます。
管理の費用は、相続財産の中から支払います。(民法第885条)
-
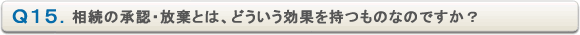
-
相続の承認・放棄とは、以下のような効果を持ちます。
1.相続の承認の種類
- 単純承認(民法第920条)
相続人が被相続人の権利義務を無限に相続すること。
- 限定承認(民法第922条)
相続財産の限度においてのみ相続債務・遺贈を弁済することを留保して相続を承認すること。相続人が数人いるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。(民法第923条)
2.放棄(民法第938条・第939条)
- 民法所定の方式に従って行われる、相続財産を一切承継しない(相続人にならない)旨の意思表示をいいます。
- 原則として、熟慮期間としての「3ヶ月」以内に、家庭裁判所に放棄の申述をし家庭裁判所で、本人自らの意思であることの確認を受けることで効力が生じます。
- 例外としては、熟慮期間経過後に、被相続人の相続財産が、債務超過であることが、相続人において過失なくして、判明した場合には、その債務超過が明らかになった時から、起算することになります。(最高裁判例)